移ろい征く空の色
上.青空を塗りつぶした夜 一章.週末には薔薇の花束を
009.花の便りは風に乗って
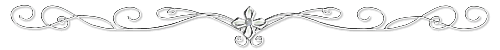
リエラベスクの街を発って早五日。辿り着いたるは広大な平原の、僅か北側に位置するジャレスの町。
平原とはいえ、そこは荒野にも近い寂れた土地が果てしなく広がるだけ。そんな場所のすぐ傍だから、町はぽつりと所在なさげにそこにある筈だったのだ。
その筈だったのだけれど。
既に時刻は夕暮れ時。太陽が赤く染まりながら地平線のベッドに身を沈める時間。だというのに、町はそんな事実にそぐわず俄かに活気付いていた。
大通りを彩る花飾り、色とりどりの旗印。赤に照らされつつも、いつになく艶やかな色彩と雰囲気が町全体を包み込む。
そして通りのあちらこちらには、これまたいつになく浮かれた様子で大通りをねり歩く、町の住人の紳士淑女少年少女老爺老婆達の姿。つまるところ老若男女問わず。
誰もが普段とは違う鮮やかな衣装に身を包み、その多くが手に薔薇を携えていた。
赤、白、黄。種類は違えど、大まかに分けてその三色。
薄紅ではなく、燃えるような、情熱的な赤。
混じり気ひとつない、純粋な白。
咲き誇る向日葵の花にも似た、鮮やかな黄。
花は、その存在を主張するかのように、持ち主達の元で艶やかに咲き誇っていた。
***
「しょーびさい?」
まくまくとフォークに突き刺したウインナーを齧りつつ、言葉の尻を上げて思いきり疑問調のフィルの言葉に、宿の女主人は鷹揚に頷いて応えた。
町に漸く着いたという頃が丁度夕暮れ時であったため、宿を探してついでに宿の食堂でそのまま少し早い夕食を取ることにしたのだ。
街道を行く旅の間、食事は主に穀物を粉にしたものを固めて作られた携帯食料。栄養はあるそうだが味気ない。
暖かく美味しい食べ物に飢えていたというのが、早めの夕食にした一つの要因だろう。
ひとつの円卓にフィル、ティティ、フレイ、レンの順でぐるりと座る。
食事をしつつ、夕暮れ時だというのにやたらと活気付いていた街の様子についてフィルは女主人に問いかけた。そこで返ってきた『薔薇祭』と言う言葉に、話は冒頭のフィルの台詞へと至る。
薔薇祭(しょうびさい)。それが、その日街で行われている祭の名だった。
元々はこの地方の特産品である薔薇を使って客寄せができないかと画策し、生み出された祭なのだそうだが、今ではこの祭のためだけに大量の薔薇が栽培されているのだという。目的と手段が逆になった典型的な例である。
後に続いた説明によって、街を歩く人々の誰もが薔薇を身につけているその理由がわかった。
この祭ではその薔薇を使って、一風変わった告白が街の至る所で行われているのである。
曰く、赤薔薇を告白の代わりに思い人に渡し、受け取った方は思いを受け入れるならば白薔薇を、断るのなら黄色の薔薇を返事の代わりに渡すのだとか。
赤薔薇の花言葉は『愛』。白薔薇の花言葉は『相思相愛』。黄色の薔薇の花言葉は『恋の終わり』。花言葉を使って思いを伝えさせるとは、思いついた人は粋なことを考えたものだ。
言われてみれば、外を通る人の様子でも何となくそのことが窺い知れる。
少し緊張した面持ちで赤薔薇を手に持つ少女の姿、嬉しそうにはにかみながら白薔薇を受け取る男性の姿、がっくりと項垂れるように黄色の薔薇を握る少年の姿。その心境が手に取るようにわかる光景だった。
「で、どうだい? 祭は明後日まで続くけど、あんた達も参加してみないかい?」
「残念だけど遠慮しとくわ。明日には買い物を済ませて平原越えに入るつもりだから」
大体旅人が誰に薔薇を渡すというのだ、誰に。
確かに、いずれはどこかの町だか村だかに永住し、ひょっとすると誰かと所帯を持ったりするのかもしれない。だが今はそんな気など毛頭ないし、また想像もできない。
恐らく四人共が、頭の中でひっそりとそう思いはしただろう。しかし口にするのは憚られたためか、考えを表には出さずにフィルは宿の気さくな女主人に返す。
女主人は軽くあしらわれたことに対する不快は感じなかったようだが、何かに気づいたように『おや』と声を上げた。
「明日って……祭の間は普通の店は開いてないよ? せいぜい出店がいいとこさ」
「へー店が開いてない……って嘘っ!?」
「こんなことで嘘言ってどうしようってのさ。
多分祭の間は食堂か花屋くらいしか開いてないだろうねえ。
まあ、旅人さんには祭に当たるなんてそうそうないことだろうし、折角だからこの際祭が終わるまでゆっくり楽しんで行ったらどうだい?」
拍子抜けするくらい気楽に言ってのけた女将は、まだ仕事が残っているのかそのまま踵を返して去っていく。忙しいのだろうか、足取りはどことなく泡だたしい。
彼女が振り向きもせず去った後には、今にも風化して灰になりそうなフィルの姿が残っていた。
誰もが気まずそうに言葉を詰まらせる。そして最初に口を開いたのは、やはりフレイだった。よく気のつく人間というのは、時に損な役回りでもある。
「えーと、あー、フィル? 大丈夫? ……ってか、その、元気出して……ってのも何か変な気もするけど……」
「そうですよ! ほら、お祭もあることですし、折角ですから楽しんでいきましょうよ!」
「というか、神殿からの使者が来るという時に祭なんかやっていられるのか?」
…………
何と言うべきか、この男は本当に間が悪い。ここまでくると、寧ろわざとやっているのではないかと思うほどだ。
最早毎度お馴染みとなりつつあるパターンの予感を感じ、フレイは椅子を引いてその場から退避した。
そして思わず嘆息。嘆息ついでにテーブルの上のバスケットからパンを一つ手に取り、ちぎって口に入れた。手作りのパンが香ばしい。ごく普通の夕食に、泣きたくなるくらいの平和を感じた。
隣では本能的に危険を察知したのか、ティティが同じように椅子を引く。それは確かに、賢明な判断であった。途中でテーブルの脚に自分の足を引っ掛けて後ろにひっくり返りさえしなければ。
咄嗟のことであったため、フレイに出来たのはぐらついたテーブルが倒れないように支えてやることだけだった。
右から左から、騒々しい物音が響き始める。例えるならスパーンだとか、どんがらがっしゃんだとか。
こんなんで、これから先大丈夫なのだろうか。
フレイは先行きに多大なる不安を覚えたのだった。
***
台詞は何の脈絡もなく、降って湧いたかのようにぽんと投げ出された。
「多分、お祭の間はあの人達も手を出してこないと思うんですよ!」
あの人達って誰だ、あの人達って。話に脈絡がなさすぎる。
「……突然何よ」
ティティの言葉は実に唐突だった。これではフィルでなくともそう突っ込みたくなるだろう、と言えるほど。
既に夕食は終わり、そろそろ引き上げようかと部屋に戻ってそれなりの時間が経過している。湯浴みも終え寝衣にも着替えて、現在はベッドの上でいつでも寝られる態勢が整っていた。
そしてここは二部屋借りたうちの一部屋。一部屋は男二人が泊まっているため、当然この部屋にはフィルとティティの二人しかいないわけで。
フィルの考えを代弁するとすれば、この話題はもう『今更』な話なのだ。
「いえ、さっき言うの忘れてたんですけどね、実はここのお祭ってかなーり有名なんですよ。それこそ他の大陸でも知ってる方がいるくらい」
「へー…………で?」
話が掴めない。
訝しむ表情を隠そうともせずに、フィルはティティに先を促す。
「あのですね、このお祭で使う薔薇ってこの辺りの土でしか上手く育たないらしくて、この街の近くでしか栽培してないらしいんです。しかもこのお祭でしか売り出されないから、随分遠くの方からも貴族の方達が買いに来たりするそうなんですよね。
もしお祭が中止になっちゃったら、その薔薇も買えなくなっちゃいますでしょ? だから……」
「つまり、神殿側としては祭を中止にしてでもさっさと巫女さん探し出したいとこだけど、そんなことしたら期間限定商品の薔薇が売り出されない。それで貴族側から圧力がかかるから、やむなく延期せざるをえないってわけね」
なるほど、納得だ。漸く得心がいったというようにフィルが続けた。気が短い所為で誤解されがちだが、元より彼女は頭も察しもそう悪いわけではない。
時間をおいて冷静になれば、情報を手に入れてそれから状況を的確に判断する能力とてある。
「そういうことです」
「なるほどね。それなら祭が終わった次の日朝一番にでも買い物をすませて出て行けば間に合うかもしれないわ」
「ですよね」
ほっとした表情で笑うティティに、随分気を遣わせてしまったものだとフィルは苦笑した。見た目が十代前半の少女なだけなおさらだ。
気を遣わせてしまったと言えばフレイもだ。彼は見た目や喋り方こそごく普通の少年だが、年不相応、外見不相応に周りの空気を読む能力に長けている。まだ若いというのに損な性分だ。
ちなみに、レンは完全に対象外。フィルの中でレンは人に気を使ったりしない人種だと認識されているらしい。概ねその通りではあったが。
ああ見えて実は色々と考えているのだ、と言われようと、そう見せかけて実はやっぱり何も考えていないんだろうと思う。
「そう言われてみればこの時期、確かフランベルクの城にも薔薇が運ばれてたわね。それもやたらと慌ただしく」
「珍しい薔薇ですから勿論王家の方々にも献上されますからね。何でも切り花じゃあ長持ちしないから、ごっそり株ごと運ぶらしいんですよ。気候が合わないらしくてどちらにせよ長持ちはしないそうですが……ってフィル、何でそんなこと知ってるんですか?」
「あら、言ってなかった? 私、カセルドの出身だもの」
当然とでも言うようにさらりと答えたフィルに、今度はティティが納得したような顔をした。軽く握った右手で左手の掌を打つという非常にわかりやすい動作付きだ。
カセルドは王城の存在する大陸である上に、大陸面積は世界最大を誇るここ、クイスナ大陸のおよそ7分の1以下とずっと狭い。
ある程度の大きさのある街にはすべて街道が通っていることもあり、情報の伝達が速く、大陸の隅まで及んでいるのは至極当然のことだ。
「そうだったんですか。随分と遠いところからいらしたんですねぇ」
「遠いとこって、旅人なら割と普通だと思うけど。師匠は確か四大陸は制覇したって言って……」
そこではっと何かに気づいたかのようにフィルの言葉が止まった。そのままベッドの隅に蹲り体を丸めて唸りだす。かなり挙動不審だ。
ティティはかくん、と首を傾げる。
「フィル?」
「ちょっと待って今余計なことを口走っちゃったから。あー消え去れ忌わしい記憶共め……!」
「……フィルにはお師匠さんがいらっしゃるんですか?」
「イヤー!! そのことは話題にあげないで! 地獄の日々が蘇るうぅ〜!!」
今度は頭を抱えてがたがたと震えだした。何だか薬の末期症状の患者みたいだ。
扱いかねたティティがおろおろと慌てていると、不意にフィルの震えが止まった。
「……寝ましょ」
「はい?」
「何も考えずとっとと寝て、明日は祭にでも行ってぱーっと全部忘れましょ。そうよそれがいいんだわ」
「は、はあ」
「じゃあ、おやすみ」
言うや否や、フィルはぱったりとベッドの上に横になった。
そのまま身動ぎひとつしないところを見ると、どうやら本当に寝入ったらしい。自分一人起きていても仕方がないので、ティティも枕に頭を埋めゆっくりと目を閉じた。
ティティはとても寝つきがよかった。
だからその夜、フィルが『鬼……』や『こ、殺される……!』などといった、内容に少々問題のある寝言を言っていたことは、彼女の知る由もないことだった。
